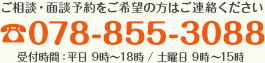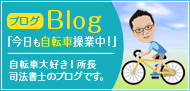相 続
神戸六甲わかば司法書士事務所は、もちろん相続登記の依頼も承っておりますが、それだけではありません。
神戸六甲わかば司法書士事務所は、依頼者の必要性に応じた最適な相続準備及び相続執行手続(遺言執行、相続財産清算事務及び任意財産管理)をお手伝いいたします。相続に関するお悩みがありましたら、是非一度 神戸六甲わかば司法書士事務所にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ電話番号 :078-855-3088
受付時間:平日9:00~18:00
相続を準備する必要性
自分の死後に財産をどのように承継させるかという問題は、特に次のような場合に現実味を帯びてきます。
- 推定相続人に財産を承継させたくない事情がある場合
- 会社の経営権の承継を伴う場合(事業承継)
- 自分の死後に、監護を必要とする家族が遺される場合
- 相続税対策の必要がある場合
相続前の準備として、生前贈与、死因贈与契約、遺言、信託(遺言信託、遺言代用信託)を始めとした様々な手段(の組み合わせ)を用いることができます。
相続(または遺贈)開始後の注意事項
1.遺言の有無
人が亡くなったときには、遺産の所有権が移転します。
この時、遺言書の有無により 次のような問題が生じます。
| ◎遺言書がある場合 | まずは、遺言書としての形式を満たしているか否かを確認する必要があります。公正証書で遺言書が作成された場合、遺言書の形式的要件を満たさないことは稀でしょう。しかし、自筆証書(読んで字のごとく、「遺言者自ら手書きした証書」という意味です。)で遺言書が作成されている場合は、注意が必要です。自筆か否か、日付が記載されているか、押印があるか等(民法968条等)の要件を満たさない遺言書は、無効なものと判断される恐れがあります。また、遺言書の効力の問題とは直接関係ありませんが、自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認手続き(民法1004条)を受けてください(勝手に開封してはいけません。)。 次に、内容に関しても、特に自筆証書遺言は注意が必要です。準拠法が何であるか(外国人の相続案件の場合)、遺言執行者は誰であるのか、遺留分を侵害する内容であるか、財産の特定はされているか等、注意すべきです。 実際に相続が発生する時のトラブルを回避するためにも、遺言書は、専門家の関与のもとに作成すべきでしょう。 |
| ◎遺言書がない場合 | まずは、法定相続人が誰であるかを確定する必要があります。 被相続人とは、遺産を遺した人、つまり亡くなった人のことです。 被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法第890条)。ただし、戸籍上に入籍していることが要件ですので、いわゆる内縁の妻や離婚した前妻には相続権がありません。 誰が相続人となるかは、次の順位に従って定まります。先順位の者がいる場合には、後順位者は、相続人にはなりません。 第1順位 被相続人の子(子が死亡している場合は子の子) 第2順位 被相続人の父母(父母がいない場合は祖父母) 第3順位 被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合は兄弟姉妹の子) 法定相続人の確定に困難を伴うのは、以下のような場合です。 ・相続開始(被相続人が亡くなった時)から長期間経過してしまった場合。 ・被相続人が、離婚・再婚・縁組等をしていた場合。 ・被相続人が在日外国人で、準拠法が外国法である場合。 ・被相続人が在日外国人で、本国戸籍の取得が困難である場合。 例え、相続人が確定したとしても、以下のような場合には、手続き進行に困難を伴うことがあります。 ・共同相続人の中に、外国居住者がいる場合。 ・共同相続人の中に、行方不明者・生死不明者がいる場合。 ・共同相続人の意思が統一されていない場合。 ・共同相続人の中に、事理を弁識する能力を欠くものがいる場合。 その他、相続税の問題にも気をつける必要があります。 |
2.相続財産の確定
生前に被相続人が財産を独りで管理していた場合、保有資産が多岐にわたる場合、事業を営んでおり取引先との債権債務関係が複雑である場合等、相続財産を確定することに困難を伴うことがあります。
3.税金の問題
相続手続き及び相続準備手続きを行ううえで、税金の問題は最大の関心事です。(詳しくは、下記を参照してください。神戸六甲わかば司法書士事務所では、必要に応じて、税理士等の専門家と連携して、相続手続き及び相続準備手続きを行います。)
相続税の問題
1.相続税納税義務の生じる相続
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して課税されます。課税される場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に応じた相続分により計算します。
実際の計算に当たっては、民法に定める相続分(法定相続分)によりあん分した額を下記(2. 相続税改正の影響)の速算表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の基となる税額となります。この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額になります。
2. 相続税改正の影響
相続税の基礎控除の額は大きいので、相続税の対象となるのは相続件数全体の「5%」といわれ、よほどの資産家でなければ実際には相続税の心配はありませんでした。
従来、相続税の基礎控除額は、
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数
となり、税率は下記速算表のとおりです。
◎2014年12月31日までの相続税の税率と控除額(速算表)
| 課税遺産×各相続人の法定相続分 | 税率 | 控除額 |
| ~1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超~ | 50% | 4,700万円 |
例えば、被相続人に、配偶者と子供2人の共同相続人がいる場合を考えてみると、基礎控除額は、
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
ですので、大雑把に言えば、8,000万円以上の相続財産がない限り、相続税がかかりません。
しかし2015年(平成27年)1月1日以後に開始した相続に関して、改正相続税法が適用されます。
また遺産額が1億円超の税率と控除額も細分化されます。
2015年(平成27年)1月1日以降開始した相続に関して、相続税の基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
であり、改正法による税率は下記速算表のとおりです。
◎2015年1月1日以後の相続税の税率と控除額(速算表)
| 課税遺産×各相続人の法定相続分 | 税率 | 控除額 |
| ~1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
先程と同じく、法定相続人の数が3人だとすると、基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 3人=4,800万円
です。
基礎控除額の縮小に伴い、相続税の課税対象者の範囲は大幅に拡大します。相続税対策が、決して一部の富裕層だけのものではなくなったと言えるでしょう。
3.相続税の計算手順
- 積極財産-(非課税財産+債務+葬儀費用)=遺産額
- 遺産額+相続開始前3年以内の贈与財産=課税価格
- 課税価格-基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)=課税される遺産額
- 課税される遺産額を法定相続人の数で分配(実際の配分に関係なく)
- 分配された課税遺産額×相続税率 ⇒ この額を合計する=相続税の総額
- 相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分-税額控除=相続税額(納税額)
下記のような条件のもと、上の手順に当てはめて具体的に計算してみましょう。
<条件>
- 相続人:相続人3人(配偶者・子供2人)
- 相続財産:不動産・預貯金など相続税評価額 6億円
非課税財産 4,000万円
債務 7,500万円
葬儀費用 500万円
相続開始前3年以内の贈与財産 6,000万円
<計算>
- 6億円-(4,000万円+7,500万円+500万円)=4億8,000万円
- 4億8,000万円+6,000万円=5億4,000万円
- 5億4,000万円-(5,000万円+1,000万円×3人)=4億6,000万円
- 4億6,000万を法定相続分で分配:
配偶者(1/2) 2億3,000万円
子供(各1/2) 各1億1,500万円 - 配偶者(2億3,000万×40%-1,700万)+子供(1億1,500万×40%-1,700万)×2人=1億3,300万
- 仮に、法定相続分と同じ割合で相続財産を承継したと仮定すると、
配偶者納税額:1億3,300万×(1/2)=6,650万
各子供の納税額:1億3,300万×(1/4)=3,325万
ただし、配偶者の場合は、「配偶者の税額軽減措置」により、配偶者の承継する相続財産が1億6,000万円以下、または、法定相続分までの割合で相続した場合は、税負担はありません。よって、上の例(配偶者の相続分が法定相続分と同じ)でも、配偶者に対して、相続税はかかりません。
4.相続税対策
相続税の基礎控除額の改定に伴い、相続税課税対象者となる人の範囲は拡大します。このことから、今後、相続税対策は、普通の人にとっても一層身近なものになることが確実です。以下、相続税対策として基本的な5つの方法を述べます。
| 対策 1. | 相続人を増やして税率区分を下げる | 相続税は累進課税の段階税率になっていますから、一人当たりの相続額を少なくして低い税率区分にあてはまれば、納税額はがくんと減ります。また相続人が一人増えるごとに基礎控除額が1000万円(平成27年1月1日以降開始した相続に関しては、600万円)追加されます。すなわち、相続人の数を増やせば全体の相続税を減らすことができるわけです。 相続人の数を増やすために用いられる方法が、「養子縁組制度」です。養子縁組をすることで、相続人の相続分が細分化されます。民法上は、養子縁組は何人でも可能ですが、相続税法では、実子がいる場合には養子は何人いてもまとめて一人になり、1000万円の基礎控除額の加算が認められます。ただし、実子がいない場合は2人まで認められ、基礎控除額は2000万円になります。 このほかにも、相続人の数を増やせば、生命保険と退職金の非課税枠(法定相続人一人500万円)が増えます。 |
| 対策 2. | 所有財産の評価額を下げる | 土地・建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により財産評価(相続財産・固定資産としての課税上の評価であって、売買評価ではありません。)が下がります。例えば、更地は、宅地よりも課税上の財産としての評価は高くなります。 そこで、更地で土地を持っている場合は、そこに建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることができます。アパートやマンションを建てて人に貸すことは、典型的な相続税対策として多く用いられています(建築費を、金融機関からの融資で賄うことで、節税効果をより高めます。)。これは所得税及び固定資産税の節税対策としても有効な手段です。 また小規模宅地等は50パーセントの評価減がされますが、一定の条件を満たすと、特定居住用小規模宅地として80パーセントの評価減になります。この条件にあてはまるような土地活用を行えば、土地の評価額が下がりますから、相続税額も下がります。 |
| 対策 3. | 借金をする | むやみに借金を勧めるわけではありませんので、勘違いをしないでいただきたいと思います。しかし、借入金の残額は、相続財産から全額控除することができるので、相続税を大きく減額する効果があることは事実です。 例えば、上記2で述べたように、金融機関からの借入を建築資金として、更地にアパートを建てるような場合、相続税の節税効果はさらに高まります。ただし、借金すべきか否かという問題は、金利水準、返済可能性、節税効果や収益可能性等の様々な要素が複雑に絡み合った問題ですので、税理士等の専門家と相談のうえ判断してください。 |
| 対策 4. | 生前贈与をして財産を減らしておく | 相続財産とは、原則として、相続開始時(死亡時)まで被相続人に帰属していた権利義務のことを言います。従って、相続開始より前の時点で、被相続人が、財産を手放しておけば、それは相続財産ではないということになります。相続財産となるべき財産を減らすためには、(生前)贈与という方法が用いられます。 もちろん、無制限に生前贈与を認めてしまうと、相続税という税目自体が骨抜きになってしまいます。そこで、税法は、相続税の補完として(相続税脱税予防策として)、比較的高率の贈与税を定めているのです。また、税法は、固有の意味での相続財産のほかに、一定範囲の財産を相続財産と「みなす」ことによって、相続税の免脱を防止しています。例えば、被相続人から相続人や受贈者に対して相続開始時点から前3年以内に贈与されたものは、相続財産とみなされ、相続税の課税対象財産算定の基礎となります。よって、生前贈与をするか否か、また生前贈与するとしても、いつ、どのくらいの規模で、誰に対し贈与するのか、という問題は、贈与税を睨みながら決すべき問題です。 まず選択肢として、「暦年課税」を用いるのか、「相続時精算課税」を用いるのかという問題があります。暦年課税を用いるのなら、年間110万円までの贈与税の基礎控除を利用することができます。また、親子孫間や夫婦間の贈与では、活用できる特例がいろいろあります。一方、相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。相続時精算課税を利用した場合、贈与税の控除枠が2,500万円まで利用できますので、贈与税の節税効果はあります。しかし、相続税の節税にはなりませんので、注意しましょう。 |
| 対策 5. | 納税資金として生命保険と自己株式を活用する | また、資産家が亡くなった場合などに多額の相続税をどのように納めるか、という問題も、相続税対策の一つです。原則は、現金で納税することになります。例外的に、相続財産の中身が不動産など、流通性のある財産である場合、現物で収めるということも可能です(「物納」と言います。)。原則通り、現金で相続税を納めるとなると、そのための準備として、大口の生命保険に加入するということがよく行われる方法です。この方法によれば、相続が発生するとすぐに納税のための現金が用意できます。
また、保険の掛け金を払うことによって、相続財産を減らす効果もあります。ただし、「相続財産を減らす効果」とは、支払った保険の掛金全額について生じるのではありません。なぜなら、仮にそのようなことが許されるとしたら、生前に財産のほとんどを生命保険の掛金として使ってしまえば、どんな資産家でも相続税を簡単に免脱してしまえるからです。このような相続税の抜け穴を作らないために、税法上は、被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続財産と「みなされ」ています。しかし、この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるときは、その超える部分のみが相続税の課税対象になりますので、節税効果は残るようになっています。なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税枠の適用はありません。 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 また、事業を経営している人の場合は、自己株式(金庫株)や退職金を利用して、相続税の納税資金を捻出する方法もあります。自社株の物納も不可能ではありませんが、譲渡制限株式は物納することはできません。自己株式の利用とは、相続人が相続した自社株を会社に買い取ってもらい、その売却代金で相続税を納税するというものです。会社に買取り資金があれば、自社株を譲渡した株主に対する課税も軽減措置が設けられているため、有効な納税資金対策となります。 なお、会社は資金の手当てができれば、いくらでも自己株式を取得できるわけではありません。会社法では、自己株式の取得は剰余金の配当などの財源規制を受け、また、会社の純資産額が300万円を割ってしまうような自己株式の取得はできませんので、注意が必要です。 さらに、事業経営者が相続を準備する場合には、経営する会社から退職金を受け取れば、老後の生活資金として消費した残りは相続税の課税対象となる相続財産を構成するとともに、相続人が相続税の納税資金として活用できる現金となります。 また、死亡の時まで会社に在職していたとすれば、死亡退職金を相続人に支給することができます。これは、相続税の課税財産とみなされ、相続税の課税対象となる(一定範囲の非課税枠があります)とともに、相続人が相続税の納税資金として活用できる現金となります。 このほか、会社が支給する一定範囲内の弔慰金は、相続人が現金を受け取れるにも関わらず、相続税の非課税財産となります。 |
贈与税の問題
1.贈与と税金
贈与を行おうとする場合に、最も気をつけなければいけないのは、贈与税の問題です。贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」(原則)と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
原則として、贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
2.相続時精算課税制度
親から子へ財産を贈与するときなどには、「相続時精算課税」を選択することができる場合があります。「相続時精算課税」を選択した場合、贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除し、その残額に対してのみ課税されます。なお、「相続時精算課税」を選択する場合には、期限内に、必ず贈与税及び相続時精算課税制度を利用する旨の申告をしなければなりません。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。(相続時精算課税方式を利用しても、贈与税の節税になるだけで、相続税の節税には効果がないことは、上記「相続税の問題」項の「4.相続税対策」の「対策4」で述べたとおりです。)
3.夫婦間贈与の特例
その他、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
贈与税は高率の税金ですので、相続準備として贈与を計画するのであれば、税務にも気をつけて万全の計画を立てる必要があります。
相続に関わる財産管理業務・遺産整理業務
相続に関わる財産業務として、司法書士は次の財産管理業務を行います。専門家が、相続財産の管理業務を行うことによって、相続財産に関する権利の承継手続きが円滑かつ確実に行われます。
- 遺言執行者:
遺言として遺された被相続人の意思を実現する - 清算業務代理人:
限定承認手続において、相続財産管理人(=相続人の一人)からの委任により実際の相続財産清算事務を執行する - 任意財産管理人:
相続関係が複雑であったり、相続財産が多岐に渡っている場合には相続人からの委任によりそれらの調査を行い、複雑な権利承継手続きの実務をこなす