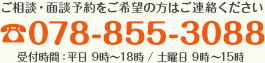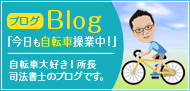遺産処分に関する遺言の定めと遺産分割の要否について
« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »
「遺言書があるから遺産分割が不要である。」とか、「遺言書を無視して自由に遺産分割することができる。」とか、極端な誤解をしている人が多いように思われます。このような誤解が生じるのは、遺産処分に関する遺言の規定方法が分かりにくいからかも知れません。
そこで、今回は、遺産処分に関する遺言の定め方と遺産分割の要否というテーマについて考えてみることにしましょう。

1 遺産に関する遺言の定めの方法
遺産の分配に関連して遺言で定める方法の主なものは、次の①~④です。これらの他に、遺産分割禁止(民法第908条)、特別受益払戻免除(民法第903条第3項)等も、遺産の分配に関連しないわけではありませんが、本稿テーマとの関連が薄いので省略します。
① 相続分の指定
② 遺産分割方法の指定
③ 包括遺贈
④ 特定遺贈
まず、①「相続分の指定」とは、民法第900条に規定する遺産に関する共同相続人の割合的権利(=法定相続分)の原則を修正することを言います(民法第902条)。例えば、Xの推定相続人が、妻A、子B及び子Cであるという場合を考えてみましょう。このとき、A、B及びCの法定相続分は、それぞれ2分の1、4分の1、4分の1となるでしょう。しかし、Xが遺言で、「A及びBの相続分を各2分の1とする。」と定めることもできます。このように、遺言者の意思によって相続分を修正することが相続分の指定です。
次に、②「遺産分割方法の指定」とは、現物分割、換価分割、代償分割等の、文字通り分割方法に関する定めのことです(民法第908条)。例えば、遺言で「不動産と株式を売却して、その代金を分けよ。」という定めをすれば、換価分割という遺産分割方法を指定したことになるというわけです。
さらに、遺言によって、「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができ」ます(民法第964条)。このような遺産の処分についての遺言の定めを「遺贈」と呼びます。遺贈には、③「包括遺贈」と④「特定遺贈」という二つの種類があります。
包括遺贈は、遺産の全部又はその割合的持分を譲渡する旨の定めのことです。例えば、「遺産の2分の1をDに与える。」とか、「遺産の全てをDに与える。」とか定めれば、包括遺贈を定めたことになります。
遺贈を受ける者(=受遺者)は、相続人以外の第三者に限られるわけではないので、相続人に対して包括遺贈しても構いません。ただし、相続人に包括遺贈する場合には、結局、相続分の指定をしたのと効果の点で差がないことになるでしょう。
これに対し、特定遺贈は、遺産中の特定の財産又は種類によって指定された財産を譲渡する旨の定めをすることです。例えば、「甲不動産をDに与える。」とか、「1000万円分の預金債権をDに与える。」とか定めれば、特定遺贈を定めたことになります。
特定遺贈においても、受遺者は相続人以外の第三者に限られるわけではないので、相続人に対して特定遺贈することもできます。
2 遺産分割の要否
(1) 指定相続分と異なる遺産分割
相続分の指定をした遺言があるからと言って、それだけで遺産を構成する個々の財産の帰属が確定するわけではありません。このことは、遺言による相続分の指定がなく、法定相続分を基準として相続手続をする場合と全く同じです。したがって、相続分の指定がされた場合、原則として遺産分割が必要です。
遺産分割の結果、たとえ個々の財産の金銭的価値にもとづく具体的な分割割合と指定相続分とが異なってしまったとしても、それは問題ではありません。例えば、相続人E及び相続人Fに対して遺言によって相続分がそれぞれ4分の3及び4分の1と指定されていた場合であっても、実際に相続が発生した後に、EとFとの協議によって、Eが遺産たる乙不動産を単独で取得すると決めてしまっても構わないということです。
つまり、相続分は、指定であれ法定であれ、遺産分割の基準の一つに過ぎないわけです。そして、この基準は、共同相続人間の協議によるのであれば、必ずしも絶対的なものとして考える必要はないということです。ただし、共同相続人間に争いがあって、家庭裁判所に持ち込まれるような遺産分割事件においては、相続分が遺産分割のための基準として重視されるでしょう。
例外として、一人の相続人に相続分1分の1を指定した場合等、遺産分割が行われないこともあります。
(2) 遺産分割方法指定と「相続させる」遺言
遺産分割方法の指定をした遺言があるからと言って、それだけで遺産を構成する個々の財産の帰属が確定するわけではありません。例えば、遺産たる「丙不動産を換価して分けよ。」のように指定してあっても、共同相続人間への具体的な換価金の分配について明らかにはなりません。したがって、この場合でも、原則として遺産分割が必要です。
ところが、遺産分割方法の指定に関しては、混乱を招くような事情があります。
公証実務において、長らく、主に不動産登記手続に関する理由(単独申請形式を利用し、登録免許税を節約するという理由)から、共同相続人に対して特定財産を「相続させる」という文言を用いた遺言を作成する扱いが一般化していました。例えば、「相続人Gに丙不動産を相続させる。」というものです。
判例(最判平成3年4月19日)は、次のように述べて、このような扱いを追認し、その法的性質及び効果を明らかにしています。
「遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合・・遺言者の意思は・・当該遺産を当該相続人をして、他の共同相続人と共にではなくして、単独で相続させようとする趣旨のものと解するのが当然の合理的な意思解釈というべきであり、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない。・・民法908条において被相続人が遺言で遺産の分割の方法を定めることができるとしているのも、遺産の分割の方法として、このような特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させることをも遺言で定めることを可能にするために外ならない。したがって、右の「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。」
つまり、判例によれば、特定の財産を「相続させる」遺言は、遺産分割方法の指定を定めたものであり、原則として相続開始(=遺言者の死亡)と同時に当該財産の承継の効果が発生し、遺産分割の余地はないということです。
この判例に対しては、「相続させる」遺言を遺贈の趣旨と解すべきであるという立場からの有力な批判がありますが、本稿ではこれ以上述べません。
(3) 包括遺贈と遺産分割
包括遺贈を受けた者(=受遺者)は、相続人と同一の権利義務を取得します(民法第990条)。よって、遺産に属する個々の財産についての帰属関係を確定させるためには、原則として、受遺者と相続人との間で遺産分割を行う必要があります。ただし、単独の受遺者に遺産の全てを包括遺贈した場合、遺産分割を行う余地はありません。
また、包括受遺者が、相続放棄(民法第990条、第938条等)によって、相続人としての権利義務を放棄することもあります。この場合には、放棄した受遺者を除いて遺産分割が行われます。
(4) 特定遺贈と遺産分割
特定遺贈が行われた場合には、原則として相続開始とともに財産承継の効力が生ずるので(民法第985条)、遺産分割の余地はありません。
特定受遺者は、「遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができ」ます(民法第986条第1項)。したがって、特定遺贈が放棄された場合には、当該財産について、共同相続人間での遺産分割が必要となります。ただし、ここでいう放棄は、民法第938条の方式(=家庭裁判所への申述)ではなくて、相続人に対する単なる意思表示によって行えばよいと解されています。
« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »