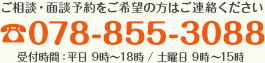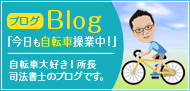「遺産共有」という概念について
« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »
相続が開始してから遺産分割によって最終的な帰属が確定するまでの間の遺産(相続財産)に関する共同相続人間の権利関係を、「遺産共有」という概念で表現することがあります。遺産共有は、財産法上の「共有」(民法第3章第3節)、「準共有」(民法第246条)及び「多数当事者間の債権関係」(民法第3編第1章第3節)との区別を明らかにするための概念です。
遺産共有は、その法的性質について争いがあり、分かりにくい概念だと思います。そこで、今回は、遺産共有について基本的な考え方を整理してみましょう。

1 遺産共有の二つの性質
共同相続人の一人は、遺産の分割前に、その「相続分」を第三者に譲渡することができます(民法第905条第1項参照)。
ここで、「相続分」というのは、各相続人が遺産共有している割合的権利のことです。相続分には、法律によって相続人の身分に応じて定められる法定相続分(民法第900条)と遺言によって定められる指定相続分(民法第902条)とがあります。
まず、相続分には、遺産を構成する個々の財産に対する共有権であるという性質があります。ただし、ここ(遺産分割が成立する前の段階)での共有権は、暫定的なものに過ぎません。さらに、相続分には、相続人の地位という身分権としての性質もあります。
例えば、相続分を同じく(各2分の1)する共同相続人AとBがいたところ、Aが第三者Cに対してその相続分全部を譲渡したという場面を考えてみます。この場合、Cは、遺産中の個々の財産に対する持分2分の1の暫定的な共有権を得るとともに、Bとの間で遺産分割協議することのできる身分を取得するわけです。
2 遺産共有されている財産の処分
(1) 処分の可否
相続開始から遺産分割成立までの間に長い期間を要したり、遺産分割が行われないまま更に重ねて(=数次に)相続が開始したりすることは珍しいことではありません。このようになってくると、本来暫定的な遺産共有の状態のまま、一部の共同相続人が、遺産を構成する個別財産の共有権を第三者に対して譲渡することも起こります。しかし、そもそも、最終的な帰属が確定していない財産を処分するということが可能なのでしょうか?
この問題に対しては、民法第909条が遺産分割の遡及効を制限する規定を置いている(「ただし、第三者の権利を害することはできない。」)ことから、処分の結果として第三者が生ずることは織り込み済みであると解されています。つまり、遺産共有の状態でも個々の財産の共有権を処分することは可能であるということです(通説)。したがって、遺産分割を経ずとも、遺産を構成する個々の財産(の共有権)の帰属が、一部の共同相続人の処分行為によって確定してしまうこともあるわけです。
(2) 第三者対抗要件の要否
遺産を構成する個別財産の共有権を処分することが可能であるとして、処分の当事者でない共同相続人は、第三者に対して処分対象財産についての共有権を、対抗要件なしに主張することはできるでしょうか?遺産共有の状態で、共同相続人が個々の財産について対抗要件(民法第177条、第178条、第467条等)を備えていることは稀であることから、もし対抗要件を要するとするならば、共同相続人の保護に欠けることになってしまうでしょう。
例えば、相続分を同じく(各2分の1)する共同相続人AとBがいたところ、Aが遺産中の甲不動産について、偽造の遺産分割協議書によってAが単独相続した旨の所有権移転登記を経由した後、第三者Cに対して甲不動産を譲渡したという場面を考えてみます。このとき、Bは、Cに対して、自らの甲不動産に対する持分2分の1の共有権を登記なしに対抗できるでしょうか?
判例(最判昭和38年2月22日)は、上のような事例において、共同相続人Bは、登記なくして自己の法定相続分に応じた甲不動産の共有権を第三者Cに対抗することができると判断しました。その理由としては、AはもともとBの持分については全くの無権利であるから、甲不動産を譲渡したとしても、登記に公信力のない日本の制度のもとでは、CがBの持分まで取得することはないというものです。
さらに、同じ理由で、遺言による相続分の指定がされていた事案においても、共同相続人は、登記なくして自己の指定相続分に応じた不動産の共有権を第三者に対抗することができるとされています(最判平成5年7月19日)。
共同相続人と第三者との利益衡量の観点や、遺贈の場合に対抗要件が必要であると解されている(通説)こととの衡平から、後者の判例に対しては有力な批判がありますが、本稿ではこれ以上述べません。
3 遺産分割か?共有物分割か?
遺産共有の状態を解消して、遺産を構成する個々の財産の帰属を定めるためには、遺産分割をおこなう必要があります。遺産分割は、共同相続人(及び相続分譲受人)全員によって協議することが原則です(民法第906条)。
しかし、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、共同相続人の一部から他の共同相続人全員を相手として、家庭裁判所に対して遺産分割を申し立てることができます(民法第907条第2項)。家庭裁判所での遺産分割は、審判(裁判所の決定)又は調停(裁判所での当事者の和解)という家事事件手続によります。
これに対して、所有権についての共有関係を解消する方法は、「共有物分割請求」によります(民法第256条)。単独での所有権が強く保護されているのに、共有権が私人の請求によって奪われてしまうような制度が設けられている理由については、共有という状態が不安定かつ不便であり、早期に解消すべきであるという趣旨と解されます。
共有物分割請求は、共有者の一部から他の共有者全員を相手方として行います。これも原則は協議によります(民法第256条第1項)が、共有者間に協議が調わないときは、通常裁判所に対して共有物分割請求訴訟を提起することができます(民法第258条第1項)。また、所有権の共有物分割に関する規定は、所有権以外の財産権の共有(=準共有)についても準用されています(民法第264条)。
両手続が大きく違うのは、裁判の形式(決定か判決か)とその効果(既判力の有無等)です。判例によれば、遺産共有の解消は、家庭裁判所が審判によって財産の分割を定めるべきであり、通常裁判所がこれを定めてはならないとされます(最判昭和62年9月4日)。また、上記2(2)で挙げた例のように、遺産中の個別財産について第三者が生じた場合、当該財産についての共有関係の解消は、通常裁判所が判決によって決すべきことであるとされ(最判平成25年11月29日)、両手続が厳密に区別されていることが分かります。
しかし、共有物分割は、訴訟によると言っても、実体法上に法律効果(=共有物の分割)を発生させるための要件事実の具体的な定めがありません。そして、このような裁判(=形式的形成訴訟)の場合、裁判所の後見的裁量が強く要請されます。したがって、共有物分割訴訟のうえで争点となる事項も、遺産分割の家事事件手続における考慮事項(「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情」民法第906条)と実質的には大きな差がないと考えることもできるでしょう。
また、遺産分割・共有物分割ともに、その分割方法は、現物を物理的に分割(=現物分割)するものであったり、取得者が他の当事者に代償を支払う(=代償分割・価格賠償)ものであったり、対象物の換価金を分ける(=換価分割)ものであったりと、柔軟な方法を採ることができます。
4 債権と債務について
かつて判例は、遺産たる債権については、債権法の規定が当然に適用され「多数当事者間の債権関係」として処理されるので、遺産共有という相続法の問題にはならないと考えていました。即ち、債権の目的たる給付が不可分の場合には民法第428条(不可分債権)の規定に従って権利関係を処理すべきだし、可分債権の場合ならば民法第427条の規定により当然に相続分に従って分割承継されるということです。したがって、遺産たる債権については、遺産共有という状態は生じないし、故に遺産分割の必要もないということになっていました(最判昭和29年4月8日等)。
しかし、上の判例のような考え方では、共同相続人間の利益調整を図るために不便であることが従来から指摘されていました。むしろ、債権を含む遺産全体を遺産分割の対象として考え、利益調整のために(お釣りとして)債権を用いることが通常の相続人間の公平と便宜に適うはずであるという批判です。そこで、実務上は、債権を分割対象に含めた遺産分割協議が行われることが一般化していました。さらに、家事事件手続による遺産分割においても、相続人間の明示又は黙示による合意によって、債権を分割対象に含めることが一般化していました。
近時、このような批判に応える形で預貯金債権について判例変更が行われ、共同相続された預貯金債権が相続分に従って当然に分割されることはなく、遺産分割の対象になるとされるようになりました(最判平成28年12月19日、最判平成29年4月6日)。その他、判例上、当然に分割承継の対象とはならないと判断された債権には、定額貯金債権、投資信託受益権、国債等があります。
一方、相続債務に関しては、遺産共有の関係は生じないというのが一般的な理解のようです。即ち、不可分債務については民法第430条を適用し、可分債務についても民法第427条により法定相続分に従って当然に分割承継されるということです(可分債務について、大決昭和5年12月4日)。このように解される理由は、共同相続人が協議によって一方的に債務の承継者を定めてしまうのだとすれば、相続という偶然によって債権者を著しく害してしまうことになるからです。
もちろん、債権者の合意のもとに、法定相続分と異なる割合で、特定の相続人が債務を承継することは一向に構いません。特に事業関連の債務について、そのような処理がよく行われます。
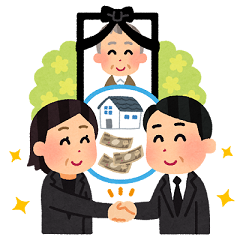
« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »