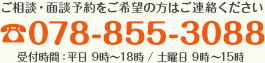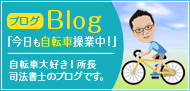不動産の時効取得と登記
« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »
長年月にわたり、自分のものだと思って使用収益してきた不動産が、見も知らない他人名義で登記されていることが判明した場合、どうしたらよいでしょう?
今回は、そのような場合に用いる「時効取得」という制度(民法第162条)と、時効取得を原因として行う登記手続きについて考えてみましょう。
1. 時効取得とは
(1)事例(以下、「本事例」という。)
Xは、一家の代々所有するとされてきた畑で、農業を営んできました。Xは、畑の名義に関して、父Aも、亡祖父Bも、自分の所有地だと言っていたため、特に疑いを抱くこともありませんでした。
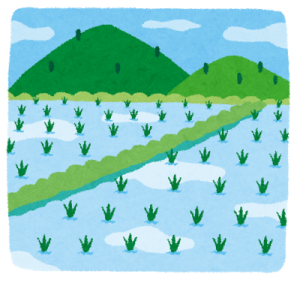
ところが、今春、父Aが死亡したことを契機として、Xが、不動産の相続登記を行うため、登記簿を閲覧してみたところ、畑の大部分を占める甲土地の所有者の欄に「Y」という見も知らない人物の名前が記載されていることが判明しました。登記簿によれば、Yは、今から50年前に相続によって、甲土地を取得したことになっています。
Xは、これから先も、従前と同様、甲土地を利用して農業を営んでいくつもりです。しかし、長年、一家の所有地だと思って手を入れてきた甲土地が、他人の物であるということには、納得がいきません。Xが、甲土地の所有権を手に入れるには、どのようにしたらよいのでしょうか?
(2)どんな状況か?
実は、対象不動産の登記簿上の名義が誰にあるかという問題と、実体法上の所有権が誰にあるかという問題は、別の問題です。そこで、本事例において、甲土地の登記簿に「所有者 Y」と記載されていながら、X(又は亡父A、亡祖父B)が、自ら所有するものであることを信じて占有を続けているという状況には、どのようなものがあるのか、以下に挙げてみましょう。
ア. 取引等による取得の場面
例えば、亡祖父Bが、有効な売買によって、Yから甲土地を買い取ったという可能性が考えられます。その場合、実体法上、所有権は亡祖父Bに移ったけれども、亡祖父BとYとが、売買による所有権移転の登記を懈怠しただけということなのかもしれません。
イ. 取引等による取得に失敗した場面
また、亡祖父Bが、Yから甲土地を買い取る契約を結んだけれども、所有権移転に必要な農地法上の許可が得られないまま、順次、亡祖父B、亡父A、そしてXによる、事実上の占有が継続されたという可能性も考えられます。その場合、本来は、Y(又はその相続人)が、依然として甲土地の所有者であることになるでしょう。
ウ. 占有開始時の権原が所有権ではない場面
さらに、亡祖父Bが、甲土地をYから借りて耕作を始めたが、亡父Aに代替わりした際に、借りたことが忘れられてしまったのかも知れません。この場合も、本来は、Y(又はその相続人)が、依然として甲土地の所有者であることになるでしょう。
エ. 占有開始時の権原がなかった場面
最後に、亡祖父Bが、自己所有地の境界を越境して甲土地を利用開始し、その状態が、誰からも異議を唱えられることのないまま、亡父AとXに代々受け継がれてきたのかも知れません。この場合も、本来は、Y(又はその相続人)が、依然として甲土地の所有者であることになるでしょう。
(3)時効取得の意味と要件
時効取得とは、「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。」(民法第162条1項)という制度です。この規定を要件に分解すると、(a)一定期間(20年)の占有継続、(b)「所有の意思」、(c)「平穏かつ公然」な占有、(d)「他人の物」ということになります。つまり、(a)~(d)の要件を充足すれば、占有者が所有権を取得することが出来るということです。
さらに、(e)占有開始時に「善意・無過失」であるときには、占有者は、(a)10年間という短期間の占有を継続すれば、所有権を取得することが出来ます(民法第162条2項)。
(b)「所有の意思」とは、物を占有する際に、権利の性質上客観的に所有者としての意思で行っているということを指します。土地を借りて占有している場合には、いくら長期間にわたって占有したとしても、時効取得しないのが原則です。
(c)「平穏かつ公然」な占有とは、暴力的な手段で占有を獲得したり、占有状態が分からないように隠ぺい工作を施したりしていないということを指します。
10年間の時効取得を主張するための(e)「善意・無過失」の要件は、自己の所有物であると信じ、かつ、そう信じることに過失がないことを指します。占有開始時に、普通ならば、他人の物であると容易に気づくような事情があるような場合、それに気付かなかったとしても過失があることになります。
ちなみに、上記の各要件について、「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する」(民法第186条1項)との規定が置かれているため、(e)「無過失」である要件を除いて、立証責任が転換されていることになります。
また、(a)一定期間(20年間又は10年間)の占有についても、「前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する」(民法第186条2項)との規定があるため、占有者は、占有開始時点と、一定期間終了時点の占有さえ立証すれば、その間の占有継続は推定されることになります。
(d)「他人の物」であるかどうかは、判例により「自己の物」にも時効取得が認められているため(最判昭和44年12月18日)、時効取得の要件として大きな意味はありません。
時効取得は、権利取得の性質から分類すれば、「原始取得」の一種に当たります。原始取得とは、自己のもとで発生する権利を取得するということです。これに対して、売買や相続などを原因として他人から権利を引き継ぐことを、「承継取得」という概念で整理します。
時効取得が成立すれば、占有開始時点に遡って、所有権取得の効力が生じます(民法第144条)。つまり、亡祖父B(又は亡父A)が占有を開始したと主張する時点で、甲土地の所有権は、亡祖父B(又は亡父A)にあったことになります。
(4)時効取得の制度趣旨と適用場面
時効取得は、1(2)ア~エのどの場面でも主張することが出来るのですが、実は、適用場面によって、その制度趣旨は一定してはいないのです。
例えば、1(2)アのように、有効な取引にもとづいて、甲土地の所有権がYから亡祖父Bへと移転していたが、登記を懈怠していたという場面を考えてみましょう。本来、このような場面では、取引法を用いて判断すべきであって、時効取得によって決すべきではありません。また、第三者が生じた場合に、所有権の帰属を決めるのは、対抗要件(=登記)の具備の前後によります。それにもかかわらず、このような場面でも、時効取得の制度が用いられる意味は、時効が登記の不備を補完することによって、取引の安全を図ることにあるのです。
1(2)イのように、取引の有効要件を一部欠いていたような場合にも、その要件を補完して取引の安全を図るという趣旨が当てはまります。
これに対し、1(2)ウ及びエのように、占有開始時の権原が所有権でなかったり、権原が全く無かったりするような場合、時効取得には、継続した事実状態を権利として認定するという意味があります。
2. 時効取得に基づく所有権の登記
(1)法律構成と登記手続きの差
時効取得は、原始取得の一種とされています。仮に、その法律構成を、そのまま登記手続きに反映させるならば、時効取得者が単独で申請人となって、時効取得を原因とする所有権保存登記を申請するのが、適当ではないでしょうか。
しかし、登記先例(明治44年6月22日民事414回答)は、時効取得を原因とする登記は、時効取得者を登記権利者、原所有者を登記義務者として、所有権移転登記を共同で申請すべきとしています。
前述のとおり、時効取得という制度の趣旨には、取引安全を補完すること(本来なら承継取得に近い)も、継続した事実状態を権利に昇華させること(本来の原始取得)も含まれています。先例は、登記技術上、これを、承継取得に準じた方法に統一しただけです。そのうえ、原所有者の権利を保護するためには、このように解した方が都合良いのです。ただし、これは単に登記技術上の問題であるので、仮に対象不動産が農地であったような場合でも、農地法上の許可を得る必要はないとされています。
また、時効取得者が原始取得する(=まっさらな所有権を取得する)反対効果として、これに矛盾する第三者の権利は、当然に消滅します。しかし、第三者の権利が登記されていた場合に、これを抹消する登記も、時効取得者を登記権利者、当の第三者を登記義務者として、共同で申請する必要があります(不動産登記法第60条)。
(2)登記権利者は誰か?
本事例において、祖父Bが、他人所有の土地であることを知りながら(=悪意で)、甲土地に越境して占有を開始し、それから5年占有を継続した後に死亡し、父Aが亡祖父Bを相続するとともに甲土地の占有を引き継いで、18年間占有を継続した後に死亡したとします。この時、Xが、亡祖父Bの占有開始から20年間の占有継続による甲土地の時効取得を主張し、これが認められるならば、登記権利者となるのは、亡祖父B(占有開始者)、亡父A(期間満了時の占有者)、X(時効援用者)のうち、誰でしょうか?
時効取得の効力が、占有開始時点に遡及して生じる(民法第144条)ということから、祖父Bが登記権利者になるようにも思われます(第1説)。また、判例は、時効期間満了時点を基準として、時効取得者とそれ以降に生じた第三者との関係を対抗問題のように処理している(最判昭和33年8月28日等)ことから、亡父Aが登記権利者になるようにも思われます(第2説)。さらに、時効の効力についての遡及効は、たんなる法の擬制に過ぎないと考えれば、単純に、Xが登記権利者であると考えることも出来るように思われます(第3説)。
上の第1~3説まで、どの考え方も成り立つでしょうが、実務は、時効期間満了時を基準とする第2説で運用されることがあるとのことです。つまり、一旦、亡父Aを登記名義人とする所有権移転登記(申請は相続人であるXが行います。)を経由した後、相続を原因としてXに対して所有権移転登記を行う必要があるということです。しかし、登記原因日付を占有開始の日と記載しながら、時効期間満了時の占有者を登記権利者とするのは、無理があるように思われます。
結局、どの説にも一応の理がありますが、どの説も確定的な根拠を欠く以上、事前に管轄の法務局と打合せをしたうえで申請を行う必要があるでしょう。特に、判決による登記を申請する必要がある場合には、請求趣旨の記載を決めておくため、訴訟提起前の段階で、法務局と打合せを行っておく必要があります。
私見では、1説が下記(3)とのバランスが取れていて、スッキリしていると思いますが、いかがでしょう?
(3)登記義務者は誰か?
本事例において、Yにも相続が生じていた場合、登記義務者となるのは誰でしょうか?
これは、登記研究の質疑回答(=法務省の役人の見解)によれば、占有開始時点を基準として判断します。
時効取得者(又はその前者たる被相続人等の占有開始者)が占有を開始する前に、所有権の登記名義人に相続が開始していた場合は、その登記名義人について相続登記をする必要があるとされています(登研質疑355号92頁)。本事例においては、亡祖父Bが占有を開始する前に、既にYが死亡していた場合には、Yについての相続登記を行わなければならないということです。つまり、Yの相続人が登記義務者であるということになります。
これに対して、時効取得者(又はその前者たる被相続人等の占有開始者)が占有を開始した後に、所有権の登記名義人に相続が開始した場合は、相続登記は必要ありません(登研質疑401号161頁)。本事例においては、亡祖父Bが占有を開始した後に、Yが死亡したのであれば、Yについて相続登記を行う必要なないということです。つまり、Y自身が登記義務者であって、相続人がYに代わって申請手続きを行うことになります。
(4)登記義務者(又はその相続人)の協力が得られない場合
登記権利者側から時効取得を主張するような場合、相手方である登記義務者側はどのような状況なのでしょうか?おそらく、登記義務者側では、数十年間という長期にわたって、当の不動産の相続登記が放置されてきたのであろうと想像されます。
登記義務者となるべきものが既に死亡しており、その相続人(又は数次相続人等)を相手方として登記手続きを行う場合、相続人の権利保護の要請から、法定相続人全員に協力してもらう必要があります(登記先例昭和27年8月23日民事甲74回答)。
しかし、相続人が相当数にのぼるような事案においては、相続人の中に反対者や行方不明者が出て、足並みがそろわないことはよくあることです。
登記義務者の相続人の中に、時効取得による登記手続きに対して反対する者がおり、話し合いで解決ができなかった場合には、最終手段として、相続人全員を相手(被告として)に、所有権移転登記手続を請求する訴訟を提起する必要があるでしょう。
さらに、相続人の中に行方不明者がいる場合には、その者をいかなる方法で訴訟という手続に「関与」させるのかも検討しなければなりません。これは、行方不明者の権利保護に関わる問題です。考えうる方法としては、公示送達又は不在者財産管理人選任という手段がありますが、それらの詳細については本稿では述べません。
時効取得の制度は、法文上、非常に簡単に規定されています。しかし、時効取得が問題となることの多い不動産の所有権について、その権利取得を登記する手続きは、一筋縄ではいかないことが殆どです。ひどい場合には、権利関係が宙に浮いたままになってしまうことも、決して珍しくはないのです。
« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »