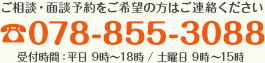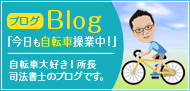配偶者居住権等の創設について(平成30年民法相続関連規定の改正)
投稿日:2018年08月06日【 不動産登記 | 相続 | 遺言 】
« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »
今般の相続法改正により、夫婦の一方が亡くなった際、他方配偶者が遺産たる自宅不動産に居住するための権利が強化されました(2020年4月施行見込)。そこで、今回は、この新制度を概観してみることにしましょう。

1 配偶者居住権等とは
(1) どのような状況か?
改正の意味を理解するため、次のような単純化した事例を考えてみます。
事例:
「甲乙夫婦が甲の所有する不動産(以下、「自宅不動産」という。)に居住していたところ、甲が先に亡くなってしまいました。夫婦に子供がおらず、甲の親も既に他界していたため、相続人となったのは、妻乙と(民法第890条)、甲とは犬猿の仲にあった兄丙(民法第889条第1項第3号)の2人です。甲の遺産は自宅不動産くらいで、現金も預貯金もほとんどありません。乙自身にも目ぼしい財産は有りません。乙は、自宅不動産に住み続けることを望んでいます。一方、丙は、相続分(4分の1)に見合う金銭での一括補償を主張して一歩も譲りません。」
当事者の話し合いによる遺産分割協議が決裂してしまった場合、家庭裁判所の遺産分割審判による解決を図ることになるでしょう。この事例においては、審判で自宅不動産の換価競売が命ぜられて、その売却益を法定相続分通りに分割することになるでしょう。しかしそうなれば、乙は住み慣れた自宅から追い出されることになり、実情に沿った「公平」な解決と言えるかどうかは疑問です。
また、遺産分割が成立するまでに長い期間を要すれば、その間、乙が自宅不動産について不安定な権利関係を強いられてしまうのも困った問題です。
今回創設された配偶者居住権等は、このような状況に対応するための制度です。
(2) 配偶者居住権
配偶者居住権(新民法第1028条第1項等)は、原則として終身の期間(=死ぬまで)、生存配偶者が無償で自宅不動産を使用収益することができる権利です。
配偶者居住権は、無償であるという点、譲渡できないという点、生存配偶者の死亡によって消滅するという点、登記請求権があるという点等が特徴的ですが、建物賃借権に類似しています。
配偶者は、次の3つの方法によって配偶者居住権を取得することができます。
ア 遺産分割協議
イ 遺贈
ウ 遺産分割審判
遺産分割協議や遺贈によって配偶者居住権を設定できるというのは、権利の性質上当然のことです。これに対して、遺産分割審判(ウ)により他の共同相続人の反対を押し切ってでも設定しうる(新民法第1029条)としたところは画期的です。
(3) 配偶者短期居住権
配偶者短期居住権(新民法第1037条第1項等)は、主に相続開始から遺産分割協議成立までの期間に限り、生存配偶者が無償で自宅不動産への居住を継続することができる権利です。建物の使用借権に類似します。
配偶者短期居住権は、法定の要件を満たせば自動的に成立する権利であって、特に合意や契約を必要としません。これに関する規定は、次の判例を昇華したものと言えます。
判例(最判平成8年12月17日):
「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。」
ただし、改正により規定されたのは「配偶者」短期居住権であるため、配偶者以外の同居相続人の居住権限については、改正法施行以降も、上記判例等にもとづいて居住権有無や代償要否等を具体的に判断する必要があります。
2 特別受益に関する改正
相続人が被相続人から遺贈又は贈与を受けた場合、当該相続人の相続分を計算するにあたって、当該遺贈等にかかる財産価値を遺産価値に含めて計算することを「特別受益の持戻し」と呼びます。これは、遺贈等の利益を享受した相続人と、それ以外の共同相続人との間の不公平を是正するための制度です。
従来から、この特別受益の持戻しについては、被相続人の意思表示(遺言等)によって適用を除外することができました(民法第903条第3項)が、持戻しが原則で、その適用除外は「持戻し免除の意思表示」をした場合の例外です。
今回の改正においては、限定的ですが特別受益の持戻しの適用について原則と例外が逆になります。すなわち、「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与したときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について・・(特別受益の持戻し)を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」(新民法第903条第4項)との規定が新設されました。「推定」されるだけの持戻し免除の意思表示を、反証によって覆すことは可能です。反証できれば、の話です。
結局、配偶者に自宅不動産を遺贈等したとしても、そのことによって他の遺産に対する当該配偶者の取り分が減ってしまうという不都合な結果は、この規定によって回避されることになるでしょう。
しかし、改正にも拘わらず、持戻し免除規定が適用されるのが婚姻期間20年以上の配偶者に限定されてしまったことについては批判も多いところです。つまり、改正法の施行後であっても、相続開始までの婚姻期間が20年に届かないことが予想されるとか、配偶者以外の推定相続人に遺贈等したいとかいう場合、遺言等によって持戻し免除の意思表示を明確にしておく必要性は依然として高いのです。
3 注意事項
配偶者居住権という新たな権利概念ができるからと言って、遺産分割でこれを定めることには改正法施行後も慎重になるべきでしょう。というのも、所有権から配偶者居住権を分離することで、相続紛争とは別の紛争の種を蒔いてしまうことになるかもしれないからです。不動産の権利を分属させることには、一般的に言って相応のリスクが伴うものです。
よって、至極当然のことですが、遺される家族(配偶者に限りません。)が安心して暮らしていけるように、予め紛争を想定して生前から準備(遺言等)しておくことが理想でしょう。配偶者居住権というのは、万策尽きたときに仕方なしに利用するものだと思います。
« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »